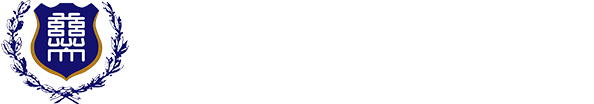- Language
- 視覚サポート
- アクセス
- 検索
- 附属病院
(本院)
- 妊娠や出産をご検討されている方へ
- お子さま・ご家族の方へ
- 診療科・部門一覧
- 医療関係者の方へ
- 母子医療センターについて
- 初期・後期研修について
出生前検査、拡大新生児スクリーニングをお考えの方へ
出生前検査とは
当院では、出生前検査の名前が世に広く知れわたる前より、検査やカウンセリングを行ってきました。多くの症例を経験した、臨床遺伝専門医や超音波専門医が中心となって、出生前検査を行っております。当院の妊婦健診は、原則当院で出産される方のみを対象としておりますが、出生前検査につきましては、他院で出産の方も受けることができます。
出生前診断とは、赤ちゃんが生まれる前に、どのような病気を持っているかを調べる検査(出生前検査)を行い、これに基づいて行う診断のことをいいます。出生前検査を行うことにより、赤ちゃんの先天性疾患の一部を調べることができます。
検査には染色体疾患の診断やリスクを判定するもの(遺伝学的検査)と脳や心臓などの臓器の異常を診断する形態学的検査(超音波検査)があります。
赤ちゃんの病気によっては生まれてからすぐに治療が必要なものもあります。出生前検査により、妊娠中に赤ちゃんの病気が分かった場合、生まれてからの治療やサポートを事前に準備することができます。また、妊娠中に治療が可能であれば治療を開始することもあります。一方で診断がつくことによって悩みが増える場合もあります。したがって検査を受ける前は、検査の合併症、検査でわかることわからないこと、対象疾患、検査を受けることの意味について十分考えていただくことが重要です。また検査結果について十分理解してその後の対応を一緒に考えることが必要です。
| 非確定検査 | 確定検査 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 検査名 | NIPT | コンバインド検査 | 母体血清マーカー検査 | 絨毛検査 | 羊水検査 |
| 実施時間 | 10週以降 | 11〜13週 | 15〜17週 | 11〜14週 | 15〜16週以降 |
| 検査の対象 | ダウン症候群 トリソミー18 トリソミー13 | ダウン症候群 トリソミー18 | ダウン症候群 トリソミー18 神経管閉鎖障害 | 染色体疾患全般 | |
| 感度※1 | 99% | 80% | 80% | 100% | |
| 結果報告までの期間 | 2週間 | 2週間程度 | 2〜3週間 | ||
| リスク/留意点 | リスクはありませんが、検査結果が「陽性」の場合、診断を確定させるために確定検査を受ける必要があります。 | 流産・死産のリスク(1/100(絨毛)〜1/300(羊水)) | |||
※1 ダウン症候群に対して(モザイク除く)。
予約について
コンバインド検査、母体血清マーカー検査(クアトロテスト)、絨毛検査、羊水検査、胎児超音波スクリーニングをご希望の方
予約先:産科外来
予約方法:当院の産科に通院中の方は、担当医にご相談ください。
他院に通院中の方は通院中の医療機関から医療連携室を通してのご予約(FAX)または紹介状を持って産科外来へお越し下さい。
出生前検査に関する遺伝カウンセリングご希望の方(どの出生前検査を行うか相談したい方、遺伝性疾患の家族歴のある方、遺伝性疾患に罹患されている方、今までに遺伝性疾患・染色体疾患のある児の妊娠・出産歴のある方など)
NIPTをご希望の方
予約先:遺伝診療部
予約方法:当院の産科に通院中の方は、担当医にご相談ください。
他院に通院中の方は通院中の医療機関から医療連携室を通してのご予約(FAX)となります。
ご予約の際は、NIPT(母体血胎児染色体検査)事前チェックリストも必要になります。
費用について
受診費用
| 検査前の遺伝カウンセリング料(初診料) | 7,700円(税込) |
|---|---|
| 結果開示時の遺伝カウンセリング料(再診料) | 7,700円(税込) |
検査費用(※1)
| 母体血胎児染色体検査(NIPT) | 143,000円(税込) |
|---|---|
| コンバインド検査 | 36,300円(税込) |
| 母体血清マーカー検査(クアトロテスト) | 27,500円(税込) |
| 絨毛検査 | 110,000円(税込)(※2) |
| 羊水検査 | 110,000円(税込)(G分染法)、169,400円(税込)(array法) |
| 胎児超音波スクリーニング | 8,800円(税込) |
※1 初再診療、妊婦健診料、処方料は含まれておりません。
※2 別途、入院費・処方料として約50,000円が必要となります。
母体血胎児染色体検査(NIPT)
当院は日本医学会 出生前検査認証制度等運営委員会より基幹施設の認証を受けて検査を行なっております。
NIPTとは、採血によって胎児の3つの染色体疾患(21トリソミー(ダウン症候群)、18トリソミー、13トリソミー)を調べる検査です。結果は「陰性」・「陽性」・「判定保留」という形で報告されます。この検査は確定的検査ではありません。「陽性」の場合は、診断を確定させるためには絨毛検査や羊水検査による染色体分析が必要となります。他院で分娩予定の方も当院でNIPTを受けることができます。
当院では遺伝診療部で遺伝カウンセリングを行い、検査の内容や対象疾患についてご案内させていただいてから、ご希望の場合は採血をいたします。NIPTを受けるかどうかはご夫婦の意思によるものです。検査を受けるにはご夫婦の同意が必要なため、お二人での来院をお願いしております。
ヘパリン投与中の方はあらかじめ担当医にお知らせください。検査費用は約14万円です。結果として「陽性」が出た場合の診断確認のための絨毛検査や羊水検査、「判定保留」が出た場合の追加検査(NIPT再検査や絨毛検査、羊水検査)の費用も初回のNIPT検査費に含まれます。
コンバインド検査
妊娠11~13週に行う検査です。超音波検査と採血による血清マーカー検査の2つを組み合わせて行う検査です。超音波検査では“首の後ろのむくみ”=NT(Nuchal Translucency)を測定します。血清マーカー検査では赤ちゃんまたは胎盤由来のタンパク質やホルモンに関する2つの血清マーカーの解析を行います。
胎児の21トリソミー(ダウン症候群)、18トリソミーの確率を算出します。年齢や家族歴などがこの確率に影響を与える因子となります。非確定的検査ですので、この結果が確定診断ではありません。
母体血清マーカー検査(クアトロテスト)
妊娠15週0日以降に行う採血での検査です。AFP、uE3、hCG、InhibinA 値より胎児の21トリソミー(ダウン症候群)、18トリソミー、神経管閉鎖障害(二分脊椎や無脳症など)の確率を算出します。年齢や家族歴などがこの確率に影響を与える因子となります。カットオフ値を基準とし、高い場合はスクリーニング陽性、低い場合はスクリーニング陰性と報告されますが、非確定的検査ですので、この結果が確定診断ではありません。
絨毛検査
妊娠11~14週に行う「確定的検査」で、胎児の染色体疾患や遺伝子疾患を診断します。母体血胎児染色体検査(NIPT)で陽性の場合、超音波検査で胎児異常の可能性が疑われる場合に実施します。
超音波ガイドの下、お腹に針を刺して胎盤の絨毛細胞を採取します。この際に局所麻酔を施して痛みを緩和します。
合併症として、破水、出血、子宮内感染、他臓器損傷(血管、腸管、膀胱など)が生じる可能性があります。また、流産・死産が約1/100(1%)の割合で生じるといわれています。より安全に検査を行うため、当院では1日(日帰り)入院で行っております。
検査の結果、胎盤性モザイクが疑われた場合は羊水検査などほかの検査が必要となる場合があります。
抗凝固療法(バイアスピリン、ヘパリンなど)を行っている方、血液型がRh陰性の方は必ず担当医にお伝えください。
羊水検査
妊娠15〜16週ごろより行う「確定的検査」です。羊水を採取することにより、胎児の染色体疾患や遺伝子疾患を診断することができます。
超音波ガイドのもと、お腹に針を刺して羊水を採取します。この際に局所麻酔を施して痛みを緩和します。
合併症として破水、出血、子宮内感染、他臓器損傷(血管、腸管、膀胱など)が生じる可能性があります。また、流産・死産が約1/300〜1/500(0.2〜0.3%)の割合で生じるといわれています。
主に外来で検査を行いますが、状況に応じて1日(日帰り)入院で対応することがあります。入院が必要な場合は別途入院費が発生します。
染色体解析方法にFISH法、G-band法、array法があります。どの解析方法を選択するかは診察結果を元に担当医と相談し決定します。
抗凝固療法(バイアスピリン、ヘパリンなど)を行っている方、血液型がRh陰性の方は必ず担当医にお伝えください。
胎児超音波スクリーニング
胎児超音波スクリーニングは超音波検査を用いて、赤ちゃんの発育や形態学的な異常、胎盤やへその緒の異常がないかを調べることを目的としています。行う時期によって目的や評価するポイントが少し異なります。
妊娠初期の超音波スクリーニング検査は妊娠11週から13週頃に行っております。いわゆる“首の後ろのむくみ”=NT(Nuchal Translucency)を代表として、いくつかのマーカーを測定し、胎児が染色体疾患や心奇形などのリスクが高くないかを確認する検査です。
妊娠中期・後期の超音波スクリーニング検査は、妊娠19~21週・26~30週に行うことが多いです。主に胎児に形態学的な異常(脳・心臓・消化管・腎臓・膀胱など)がないかを確認する検査です。中期・後期の超音波スクリーニング検査で、気になる所見があった場合は、後日精査を行う外来(胎児外来)で、さらに精密に超音波検査を行います。
拡大新生児スクリーニング
2025年3月1日現在
東京慈恵会医科大学附属病院母子医療センターでは、当院で出生した赤ちゃんを対象にファブリー病のスクリーニング検査(対象は男児のみ)を東京都予防医学協会に依頼して有償で行っております(拡大新生児スクリーニング)。ファブリー病は近年になり治療可能な疾患となりましたが、症状から診断することが難しく治療が遅れてしまうことが多い疾患となります。1万人に1人に発症するような稀な疾患ですが、新生児期にスクリーニング検査し、適切な時期に治療導入することによって、病気をもって出生した子どもたちの予後改善が期待されます。疾患の特性および技術的な問題から、男児のみが対象となります。
ファブリー病のスクリーニング検査費用は5,000円(税込)となります。拡大新生児スクリーニングの情報を希望される場合は、産科外来スタッフ、産科病棟スタッフにお声かけ下さい。パンフレット等で情報を提供いたします。分娩で入院した際に拡大新生児スクリーニング検査の意向を確認させていただき、検査を希望された方の赤ちゃんについて検査を実施しております。検査は生後4~5日に赤ちゃんのかかとから極少量の血液を採取して行い、結果は通常1か月健診で説明させていただいております。
*これまで脊髄性筋萎縮症、原発性免疫不全症、ポンぺ病、ムコ多糖症I型(ハーラー病)・II型(ハンター病)も有償で新生児スクリーニングを行っておりましたが、東京都では2024年4月より脊髄性筋萎縮症、原発性免疫不全症のスクリーニングを、2025年3月よりポンぺ病、ムコ多糖症I型・II型のスクリーニングを、全ての新生児を対象に公費で行っております。