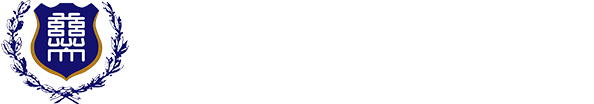- Language
- 視覚サポート
- アクセス
- 検索
- 附属病院
(本院)
- 妊娠や出産をご検討されている方へ
- お子さま・ご家族の方へ
- 診療科・部門一覧
- 医療関係者の方へ
- 母子医療センターについて
- 初期・後期研修について
不妊症・不育症でお悩みの方へ
当院では不妊症および不育症の専門外来を設けています。私たちは不妊症と不育症を別個のものとしてではなく、病態の一部を共有するものと考え、日々の診療にあたっています。この両専門外来間ではシームレスに治療を行い、さらには産科系外来とも緊密に連携をとることで、妊娠成立から出産に至るまで、継続的な医療を提供しています。
当院の特徴としては、大学病院の特色を活かし、合併症を持つ方の治療や手術を要する難治症例にも対応が可能であること。また、卵巣予備能低下症例(早発卵巣不全など)の治療に豊富な経験を持つこと、若年がん患者さんの妊孕性温存の為のがん生殖医療にも積極的に取り組んでいる点が挙げられます。
下記のようなお悩みがある方は、いつでもご相談ください。
-
避妊をしていないのに、
1年以上妊娠しない -
妊娠はするけれど流産や死産を
くり返している -
不妊について夫婦で
取組みたい
不妊症とは
生殖年齢の男女が妊娠を希望し、避妊することなく通常の性交を継続的に行っているにもかかわらず、1年以上にわたって妊娠の成立を見ない場合、不妊症と診断されます。ただし、医学的な介入を必要とする原因がある場合には期間は問われません。
不妊症の原因はさまざまです。女性のみではなく、半分近くのカップルで男性側にも原因が認められると言われています。治療にあたっては、ご夫婦で外来を受診されることをお薦めします。
不妊症外来の特徴

大学附属病院という利点を活かし、子宮内膜症や子宮筋腫、子宮内膜ポリープ等の疾患を合併している不妊症の方に対し、腹腔鏡や子宮鏡を用いた低侵襲手術を行っています。また卵巣予備能低下症例(早発卵巣不全など)の治療に豊富な経験があり、若年がん患者さんの妊孕性温存のためのがん生殖医療にも積極的に取組んでいます。
悪性腫瘍等に対する抗がん剤治療や放射線療法により、妊孕性喪失の可能性がある患者さんに対して、男性は精子凍結、女性は胚や未受精卵の凍結を行うことで、妊孕性の温存をはかります。
一般不妊治療では、年間で約300周期の人工授精(AIH)を行っています。
生殖補助医療(ART)として、体外受精(IVF)および顕微授精(ICSI)をてがけ、年間約200件の採卵治療を行っています。日本産科婦人科学会の会告に従い単一胚移植を基本とし、凍結融解胚移植も積極的に行うことで、多胎妊娠の発生減少を心がけながら、妊娠成績の向上をめざしています。
高度な生殖医療技術を追求していくことのみならず、不妊患者さんへのカウンセリングにも取組んでいます。
40歳以降の高齢不妊症例や、若年で卵巣予備能の低下を来す早発卵巣不全症例など、難治症例に対する豊富な臨床経験があるのも当部門の特徴です。妊娠をめざす治療を中心としながら、残念ながら成果が得られなかった場合の、不妊治療終結の在り方についても、カウンセリングを含めた取組みを行っています。
一般不妊治療・検査
- 不妊症スクリーニング検査(採血・卵管造影検査・精液検査)
- タイミング指導
- 排卵誘発
- 人工授精(AIH)
高度生殖補助医療(ART)
- 体外受精・胚移植(IVF-ET)
- 顕微授精(ICSI)
- 凍結融解胚移植(FT-ET)
- 医療的適応による未受精卵凍結・卵巣組織凍結
男性不妊外来
当院での治療をご希望される方へ

不妊症外来では、月曜から金曜日の8時30分~11時までに、受診してください。
前医での治療経過や検査結果がございましたら、紹介状と併せてご持参いただきますようお願いいたします。
紹介状のない初診の方も受診していただくことが可能となりますが、その際、医療費とは別に選定療養費として5,500円(税込)をお支払いいただくことになります。
当科では、主治医制ではなく、曜日担当医制で診療を行わせていただいております。土曜日は再診のみとなり、交代制での診療を行わせていただいております。
人工授精、体外受精などの治療をご希望される場合には、ご夫婦の感染症採血を行わせていただいております。
旦那さまの受診も必要になりますので、ご協力お願いいたします。(月曜から土曜日の8時30分~11時まで)
当院で体外受精をご希望の場合には、原則としてご夫婦で体外受精説明会への参加をお願いしております。
凍結胚の更新手続きの際には、ご夫婦での受診をお願いしております。
(卵子・卵巣・精子凍結の更新手続きはご本人さまのみ)卵子・受精卵凍結の更新料は年間2万円、精子凍結の更新料は年間5万円となります。
費用について
| 不妊症スクリーニング(採血、卵管造影、精液検査) | 3万円程度 |
|---|---|
| 人工授精 | 1周期3万円程度 |
| 体外受精 | 採卵20〜40万円程度 移植20〜30万円程度 |
| 精子凍結 | 5万円程度 |
(詳細は、料金一覧をご参照ください)
不育症とは
妊娠はするものの、流産や死産を繰り返し生児が得られない状態を不育症といいます。流産以外に、胎内死亡や死産を繰り返す症例も包括する概念ですが、代表的なものとして、自然流産を連続して2回以上繰り返す反復流産や、連続して3回以上繰り返す習慣流産があります。
生殖補助医療において、良好胚を繰り返し移植しているにもかかわらず妊娠が成立しない反復着床不全や、非常に早い時期の流産(生化学的妊娠)を反復する症例も不育症の概念に含めて考えることもあります。また、重症胎児発育不全、重症妊娠高血圧症候群などの胎盤機能不全が原因と思われる産科疾患もその範囲に含むこともあります。
原因は多岐に渡りますが、適切な検査と治療により、8割以上の方が生児を得ることができます。
不育症外来の特徴
まずは不育症スクリーニング検査を行います。その後、不育症の原因に応じて治療を行っています。
抗リン脂質抗体症候群およびプロテインS欠乏症などの血液凝固異常症に対するアスピリン・ヘパリン療法を中心とした抗凝固療法では最終的に約85%の成功率を得ています。
不育症検査としてご夫婦に以下の原因がないかお調べしておりますが、流産時には赤ちゃんに染色体異常がないかを調べる(流産絨毛染色体検査)ことも重要です。2回目の流産より保険診療で流産絨毛染色体検査を受けることができます(ただし、流産手術が必要となります)。ご希望の方は担当医に相談ください。
| 不育症の原因 | 主な治療法 |
|---|---|
| 子宮奇形 内分泌異常 内科的異常 | それぞれの原因に対する治療 (子宮中隔切除/ホルモン療法など) |
| 抗リン脂質抗体陽性(症候群) 血液凝固因子異常 | 漢方療法 抗凝固療法(アスピリン/ヘパリン) ステロイドなど |
| 染色体異常 | 遺伝相談 |
| 原因不明 | 心理相談/ビタミン剤/漢方など |
不育症外来へ受診ご希望される方へ
通院中の医療機関から医療連携室を通してのご予約(FAX)のみとなります。
がん生殖について
若い患者さんに対するがん治療は、その内容によっては卵巣や精巣などの性腺機能不全となり、子宮・卵巣・精巣など生殖臓器の喪失により将来子どもを持つことが困難になることがあります。医療者と患者さんにとって、最大のゴールは病気を克服することであるため、これまではがん治療によるこれらの問題点には目をつぶらざるを得ませんでした。
しかし、最近はがん診療の飛躍的進歩によってがんを克服した患者さんの治療後の生活の質(QOL=quality of life)にも目が向けられるようになってきました。
子宮がんや卵巣がんに対する子宮や卵巣を温存する手術、放射線治療から卵巣を保護する手術、さらには生殖補助技術の進歩による精子や卵子、受精卵の凍結保存などは広く普及するに至っています。
最近では卵巣を組織ごと凍結保存して、がん治療の終了後に再度体内に移植する技術も確立されつつあります。
現在、がん治療で通院中の方、これからがん治療を受ける予定の皆さんを対象に、がん治療による不妊の予防や対策についてご相談を伺います。
当院で可能な治療
- がん生殖前後の相談およびカウンセリング
- 精子凍結
- 胚(受精卵)凍結
- 卵子凍結
- 卵巣凍結
初診の方へ
がん主治医から生殖外来へ直接お電話をいただきカウンセリング候補日のご相談をさせていただいております。
受診を希望される患者さんが直接ご相談を希望される場合は腫瘍センターのがん相談センターにご連絡をお願いします。
費用について
| カウンセリング料(初診時のみ) | 1万円 |
|---|---|
| 精子凍結 | 5万円 |
| 卵子・受精卵凍結 | 体外受精料金に準ずる |
AYA生殖カウンセリング外来について

思春期・若年(AYA:Adolescent and Young Adult)世代の、がんや疾患治療後の生殖機能のフォローアップを行っております。治療方法の改善により、小児期の治療後に長期的な予後が期待される方が増えてきています。しかし化学療法や放射線治療などの一部のがん治療は、将来の妊娠に関わる卵巣や子宮への長期的な影響を与えることが知られています。当院では、治療内容に応じて卵巣機能のフォローおよび必要に応じて妊孕性温存療法を行っております。将来妊娠する可能性の評価や学校生活や社会での活動などの支援・カウンセリングなども行っています。
当院で可能な治療
- がん治療後の月経異常の相談
- 早発閉経後のホルモン療法
- 妊孕性温存療法(卵子凍結)
- がん治療後の生殖カウンセリング
受診を希望される方へ
ご両親または主治医から生殖外来へお電話をいただきカウンセリング候補日のご相談をさせていただいております。
費用について
| カウンセリング料(初診時のみ) | 5,000円 |
|---|
受診を希望される方へ
紹介状ご持参の方は、病院の初診の方への手続きと同様になります。
不妊症外来の初診は月曜から金曜日の8時30分~11時までとなっております。
不育症外来、がん生殖外来、AYA生殖カウンセリング外来は完全予約制となっております。受診に関しては、直接お電話でご確認ください。
よくあるご質問
Q再診となりますが、前回受診時から期間が空いています。どのようにしたら良いですか?
A初診から6カ月以上空いて受診される患者さんは、予約外で8時30分~11時までの間に外来へお越しください。
Q社会的な理由での卵子凍結や精子凍結はやっていますか?
A当院では社会的卵子凍結・精子凍結などの妊孕性温存治療は行っておりません。
がん診断後や抗がん剤治療前などで、医学的な理由での卵子凍結・精子凍結は積極的に行っております。主治医に相談していただき、がん生殖外来の予約を取得してください。(完全予約制となります。)
Q待ち時間はどのくらいになりますか?
A可能な限り待ち時間の短縮に努めておりますが、一般不妊治療・不育症外来で30分から1時間程度、体外受精では採血の待ち時間もあるため、1時間から1時間半程度となります。(土曜日の外来は混雑しておりますので、お時間に余裕を持ってお越しください。)
Q不育症の検査だけ行うことはできますか?
A診察を行い、該当する方には、検査を行わせていただいております。当院で検査を行い、他院で経過観察をご希望される方もお受けしております。かかりつけ医より医療連携室を通したFAXでの予約をお願いしております。保険分と自費分の2回、別日での採血が必要となります。前医での検査結果も可能であればお持ちください。